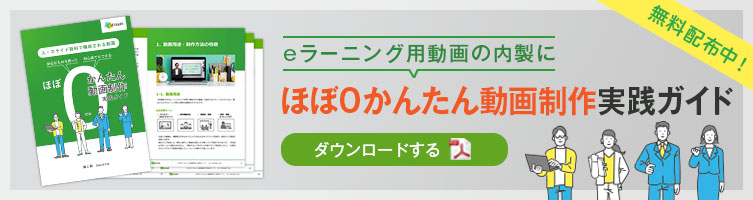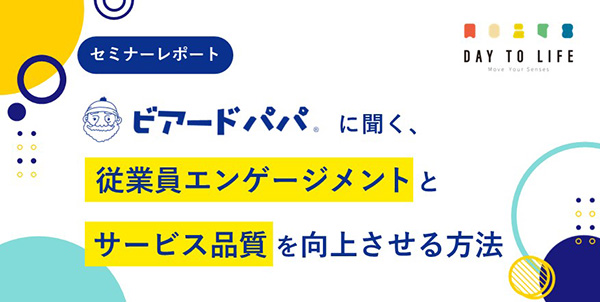eラーニングとは? 導入前に知っておくべきメリットやシステム種類や費用の解説
2022.07.26

リモートワークや時差出勤など、働き方の変化により需要の高まりを見せるeラーニング。本記事ではeラーニングの歴史や受講者と提供者それぞれにおけるeラーニングのメリット・デメリット、eラーニングシステムや教材の種類、費用なども紹介しているため、基本的なことを押えた上で導入するかどうかを判断したい経営者様やご担当者様はぜひご覧ください。
《 目次 》
1. eラーニングとは?

eラーニングとは、インターネットを介しておこなう学習方法のことです。学習にはPCやタブレット、スマホなどの端末を用います。eラーニングの受講者には「時間や場所を選ばず学習できる」「繰り返し学習ができる」といった利便性があります。
eラーニングの動画配信方法
eラーニングでは動画が用いられることが多くあります。動画の配信方法には大きく分けて「ライブ配信」と「オンデマンド配信」があります。
ライブ配信は、オンラインによるリアルタイムでの参加型学習のことです。パソコンやスマートフォン、タブレットなどのデバイスを使用して参加します。機能によっては、遠隔地のユーザー間でリアルタイムにコミュニケーションを取りながら学習をすすめることができます。リアルタイムかつ双方向のコミュニケーションを重視する場合、ZoomやMicrosoft Teams、Google MeetなどWeb会議ツールを利用して行われることもあります。
一方、オンデマンド配信は「録画配信型」のことです。配信形態はストリーミング配信が主流となっています。映画やドラマ、テレビ番組などを好きなタイミングに見られるVOD(ビデオ・オン・デマンド)サービスと同じように、動画配信サーバーにアップロードされている動画を受講者が好きなタイミングで視聴できるスタイルです。
オンデマンド(On-demand)の意味は、「要求(需要)に応じて」です。意味の通り、オンデマンド配信は、受講者側の視聴利便性がライブ配信より高く、eラーニングでは「オンデマンド配信」を採用するケースが一般的となっています。
なお本記事では、オンデマンド配信でのeラーニングに限定して解説していきます。
eラーニングに対応しているデバイス(端末)の種類
パソコンが一般家庭に普及したころは、パソコンを使ったeラーニングが主流でしたが、2000年代後半になると、タブレットやスマートフォンなどのさまざまな端末が普及し始めます。それに伴い、対応端末も増加し、近年はマルチデバイスで柔軟に受講できるeラーニングが増えている状況です。
| パソコン | タブレット・スマートフォンなど |
|---|---|
| ・大きな画面で見やすい ・机に向かって行う必要があり、学習を習慣化しやすい | ・隙間時間を有効的に活用できる ・場所を選ばずに学習できる ・直感的に操作ができ、気軽に学習できる |
パソコンとタブレット・スマートフォンのそれぞれにメリットがあり、受講者の学習スタイルにあったeラーニングを選べるようになってきています。
2. eラーニングの歴史
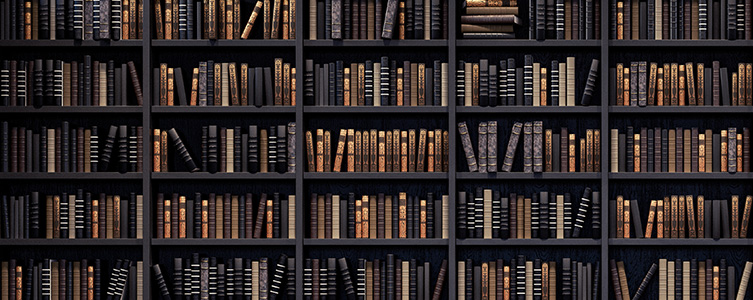
eラーニングの始まりは、1950年代に登場した「CAI(computer aided instruction)」とされています。CAIとは、コンピューターを利用した学習法のひとつです。学校や塾などにコンピューターを導入し、受講者が学習教材や教育用ソフトウェアの提供を受けて学習を進めることです。
インターネットのブロードバンド化により、高速・大容量通信が可能になった2000年代に、国内でも「eラーニング」という言葉が広がり始めます。
eラーニングが広まる前の学習形態は、講師(インストラクター)と受講者が、同じ場所・時間にいる「集合研修」と呼ばれる学習形態が主流でした。受講者の学習履歴・進捗なども人が管理する必要があり、時間や運営面における課題が多くありました。その状況を解消するために、ビデオ教材やCD-ROMを利用した学習法が登場しますが、ビデオ教材やCD-ROMも、一方的な情報の提示のみで学習者側からのアクションが行えない非対話型で、学習効果も高いとは言えません。
そのため、インターネット環境が整っていくと同時に、世界各国でコンピューターを利用した教育支援のための研究・開発が発展し、教材もCD-ROMから、Webブラウザ=インターネット接続型へとシフトしていきました。
インターネット接続により、オンライン教育が可能になったったことで、以下のような課題を解決しています。
- 学習状況などをサーバー上で一括して管理できることで工数を軽減
- 学習教材もサーバー上で配信、保管ができ、従来かかっていたCD-ROMなどのメディア配布が不要になり、配送や制作コストの軽減を実現
- プログラムの修正や学習内容の改変なども簡単にできるように
スマートフォンが普及した現在では、動画共有サービスの浸透もあり、動画で学ぶ教材が広まっています。スマートフォン・タブレットを使ったモバイルラーニング(Mobile Learning/mラーニング)もできるようになり、eラーニングはより身近になっています。
3. 【受講者側】eラーニングのメリット/デメリット

eラーニングを活用した取り組みを採用する企業が増えていますが、受講者にとってどのようなメリットがあるのかが気になると思います。
そこでこの章では、受講者側におけるeラーニングのメリットとデメリットについて解説します。受講する社員への説明やeラーニングの理解を深めるのにお役立てください。
【受講者側】eラーニングのメリット
| 受講者における eラーニングのメリット | ・移動時間や交通費が必要ない ・いつでもどこでも好きな時間に学べる ・隙間時間で少しずつ学べる ・繰り返し学べる ・「定員に達したので受けられない」ということが発生しにくい |
移動時間や交通費が必要ない
eラーニングは、環境さえ整っていれば場所を選ばず学習できます。集合型での受講であれば、講義を受ける場所までの移動時間や交通費が必要ですが、eラーニングでは、パソコンやスマートフォンなどを開けばすぐに講義を受けられるので、移動時間も交通費もかかりません。
移動にかかる時間も学習時間に充てることができ、より有効的に学習できるのは、受講者側にとって大きなメリットと言えるでしょう。
いつでもどこでも好きな時間に学べる
受講者にとってeラーニングは、オフィスや自宅、移動中など場所と時間を選ばず学べる利便性があります。スマートフォンに対応していれば、外出中でもコンテンツの視聴が可能になり、受講者個人の都合に合わせて、いつ・どこにいても学習ができます。
隙間時間で少しずつ学べる
集合研修と違い、隙間時間で少しずつ学んだり、自分のペースで繰り返し学んだりといった自由度があります。出張時の移動時間や取引先のアポイントまでの空き時間など、5分・10分程度の短い時間も学習時間となるのです。
隙間時間を有効活用することで、帰宅後などの完全にプライベートな時間を学習時間に充てる必要がなくなるため、仕事と自分の時間のメリハリが生まれます。これにより、ワークライフバランスも実現しやすくなります。
繰り返し学べる
理解できないところを何度も繰り返し学べるのは、eラーニングを使った学習の特徴です。
ライブ配信ではなくオンデマンド配信なら、自分の習熟度に合わせた速度で学ぶことができます。学習の進捗状況やテストの結果で理解度などがわかるケースが多いため、苦手分野を集中的に復習するといった使い方も可能です。
周囲を気にすることなく、自分のペースで学んでいけるのは、eラーニングのメリットと言えるでしょう。
「定員に達したので受けられない」ということが発生しにくい
オフラインの集合研修やセミナーなどの場合、日程や研修会場の広さによっては、「定員に達したため受講できない」ということもありますが、eラーニングは時間や場所にとらわれないため、リスケジュールとなる心配がありません。
研修の予定に合わせるのではなく、自分の予定に合わせられるのもeラーニングの大きな特徴です。
【受講者側】eラーニングのデメリット
| 受講者における eラーニングのデメリット | ・インターネット環境とPCやスマホなど端末が必要 ・質問がリアルタイムにできない ・一体となって学習している感覚が希薄 ・主体的に取り組まないと学習が進まない |
インターネット環境とPCやスマホなどの端末が必要
eラーニングは、どこでも学べますが、受講するためにはインターネット環境が必要です。
また、対応しているバージョンのPCやスマホといった端末の用意も必要になる点は、受講者側のデメリットと言えるでしょう。但し、近年のeラーニングはマルチデバイス対応となっていることが殆どであるため、参加者がもともと所有している端末で気軽に参加できるケースが多くなっています。
質問がリアルタイムにできない
質疑応答がリアルタイムにできない点は集合研修に劣る部分です。わからないまま放置したり、先延ばしにしたりする可能性があり、認識のズレが生じないよう、受け身の学習ではなく、受講者側から積極的にコミュニケーションを取るといった工夫が必要になるでしょう。
一体となって学習している感覚が希薄になりやすい
eラーニングでは、基本的にひとりで学習をします。そのため、集合研修のような「受講者間の一体感が少ない」という点は、受講者側にとってデメリットとなる可能性があります。
周囲の人が頑張っていると「自分も頑張ろう」というモチベーションにつながりやすい傾向がありますが、eラーニングでは周囲が頑張っているかどうかが見えづらく、「一緒に頑張ろう」というモチベーションにつながりにくいでしょう。そのため、学習にも前向きになれない可能性があります。
主体的に取り組まないと学習が進まない
eラーニングは受講者が好きな時間に学ぶことができる反面、主体的に取り組まないと学習が進まないというデメリットがあります。
「今日は仕事で疲れているから明日やろう」「今週は忙しいから、来週からやろう」このようにやるべきことを先延ばしにしてしまうと、学習もなかなか進みません。そのため、学習に対して消極的で、計画的に取り組むことが苦手な人にとっては、自由度が高いeラーニングがデメリットになる可能性があるでしょう。
4. 【提供者(企業)側】eラーニングのメリット/デメリット

eラーニングのメリット・デメリットは、受講者側だけではありません。提供者側である企業にとってのメリットも多い学習方法です。
そこでこの章では、提供者(企業)側におけるメリット・デメリットについて解説します。
【提供者(企業)側】eラーニングのメリット
| 供者(企業)側における eラーニングのメリット | ・会場費用や準備が不要 ・講師が毎回講義する必要が無い ・教育を均質化できる ・会場の広さに受講人数が縛られない |
会場費用や準備が不要
eラーニングを利用することで会場確保や準備が不要になる点は、提供者側の大きなメリットです。
企業が行っていた従来の集合研修では、参加人数に応じた広さの会場を用意する必要があり、会場代がかかっていました。教材も、印刷する場合はそのコストと手間がかかっていましたが、eラーニングによって準備にかけていた内部工数やコストの削減が見込めます。
担当者の業務負担も軽減するため、本来行うべき業務の効率化も期待できるでしょう。
講師が毎回講義する必要が無い
従来は、企業研修を行うたびに講師が稼働する必要があり、工数や外部講師を招くなら講義費用がかかっていましたが、eラーニングは過去の講義を活用することで稼働や費用の軽減ができます。
教育を均質化できる
開催ごとに講師が変わることもないので、教育を均質化できるのもメリットです。
従来は、同じテーマでも講師によって伝え方や話の深さも変わってくることから、均等な教育を提供することが難しい状況でした。会場も、座る位置によって「見えづらい」「聞き取りづらい」という不均衡が生じやすく、それが研修の理解度に影響することがありますが、eラーニングならそのデメリットの解消も見込めます。
同じ講義内容を提供することで、受講タイミングによる知識や教育の偏りがなくなり、研修の質も均質化できるのは、提供者側にとっても大きなメリットと言えるでしょう。
会場の広さに受講人数が縛られない
eラーニングを利用すれば、「小さな会場しか用意できなかったので、参加人数を制限しよう」といった不都合も生じにくくなります。
会場に左右されるのではなく、受講を希望する人全員が受けられる環境を作り出せるのはeラーニングの魅力と言えます。
【提供者(企業)側】eラーニングのデメリット
| 供者(企業)側における eラーニングのデメリット | ・eラーニングのための仕組みの導入や構築が必要 ・グループディスカッションには向いていない ・講師と受講者のコミュニケーションを取りにくい |
eラーニングのための仕組みの導入や構築が必要
提供者側におけるデメリットは、eラーニングの仕組みを社内に取り入れ、研修コンテンツをアップデートする必要があることです。
仕組みの導入については、「自社で構築するケース」と「eラーニングサービスを利用するケース」の2つがあります。
自社で構築する場合は、一から仕組みを考え、構築しなければならないため、その分の工数やコストがかかります。担当者は、eラーニングを効果的に活用するためのITスキルや知識も求められるでしょう。適任者がいない場合は、一から構築するよりも「eラーニングサービスを利用するケース」が向いています。
ただし、「eラーニングサービスを利用するケース」ももちろんコストがかかります。外部依頼にせず自社で行う場合は、研修コンテンツを作成する手間がかかるため、将来的にeラーニングをどのように活用するかまで踏まえて検討することが大事です。
グループディスカッションや実技には向いていない
提供者側視点でも「リアルタイムのコミュニケーションを前提とするグループディスカッションには向かない」というデメリットがあります。
動画や資料だけでは表現しきれない内容の講義は、eラーニングでは理解が進まない可能性もあるため、実技の習得を目的とした講義が必要な企業には向いていない場合もあります。
ただ、座学研修はeラーニングを活用し、実践やディスカッション・コミュニケーションを重視する内容は別途集合やオンライン研修を行うという形式を採用すれば、全講義を集合研修にするよりも手間とコストを軽減できる可能性があります。
講師と受講者のコミュニケーションを取りにくい
受講者側のデメリットでも伝えた通り、講師と受講者の双方向コミュニケーションが取れないというのはeラーニングのデメリットです。受講者同士のコミュニケーションも取れないため、一体感が生まれにくく、モチベーションも維持しにくいという傾向が見られます。
ただし、質疑応答は受講中にリアルタイムでおこなえないだけでeラーニングでも実現できる部分です。また、一体感についても「他の受講者の受講状況が見えるようする」「受講者コミュニティを運営する」「チャット機能があるeラーニングサービスを活用する」といった方法によりカバーできる部分です。
工夫次第でコミュニケーションの問題はクリアできるため、自社に合ったeラーニングの採用を検討しましょう。
5. eラーニングシステムと教材の種類

自社に合ったeラーニングを導入するのであれば、提供形態(システム)や教材の種類について理解しておく必要があります。
そこでこの章では、eラーニングで主流の提供形態と主要な教材のタイプについて詳しく解説します。
コンテンツの提供形態
コンテンツの提供形態は、大きく分けると次の2つです。
イントラネット型(オンプレミス型)eラーニングシステム
イントラネット型eラーニングは、自社サーバー内に学習システムを導入し、企業のプライベートネットワーク(内部ネットワーク)へアクセスして学習するシステムです。
機密性の高い資料をアップロードしても、イントラネット型のeラーニングシステムなら外部と接続しないで利用できます。そのため、セキュリティ面での不安が少ないのが特徴です。
■ イントラネット型(オンプレミス型)eラーニングシステムを選ぶ際のポイント
- 工数の確保ができるか(導入・コンテンツの準備等に時間がかかるため)
- ITスキルや知識のある担当者がいるか(自社サーバーやネット環境の整備、セキュリティ・メンテナンス管理などの専門知識が求められるため、エンジニアが必要)
- 初期導入コストに余裕があるか(クラウド型eラーニングよりも費用が掛かりやすい)
クラウド型eラーニングシステム
クラウド型eラーニングは、サービス提供会社のサーバーへインターネット回線を通じてアクセス(ログイン)してコンテンツを視聴し、学習をする形態のシステムです。
自社サーバーへのシステム構築が不要なので、導入もスムーズにでき、コストも比較的安い傾向があります。
■ クラウド型eラーニングシステムを選ぶ際のポイント
- セキュリティレベルに問題はないか(自社のセキュリティポリシーと同等かで判断)
- 利用できる人数(利用想定人数と制限数を照らし合わせて判断)
- カスタマイズ可能か(オプション・機能・ニーズに応じた仕様変更、既存教材の流用などができるかで判断)
教材のタイプ
続いては、教材のタイプです。受講対象者やコンテンツ内容により向き不向きがありますが、インプットを目的とした教材としては、次の4つがあります。
動画配信型
動画配信型は、講師が講義している様子を録画し、それを動画コンテンツとして配信する方法が主流です。
講師が話をしている様子をそのまま収録して配信するほかに、講師に加え資料画像や参考動画を加えた配信などがあります。
アニメーション型
キャラクターが講義の進行や説明を行うタイプがアニメーション型です。親しみやすいキャラクターを採用し、ストーリー性を持たせることで、アニメーションを楽しんでいるかのような感覚で学習に取り組むことができます。
アニメーション型は、企業や大人向けだけでなく、子どもや幅広い年代の人が利用するようなケースにも採用されることが多くあります。
資料配布型
講義内容をまとめたテキストや紙媒体の資料をデータ化したものが資料配布型です。従来の講義や研修で利用した資料をそのまま流用し、実施される場合が多く見られます。
制作の手間がかかりにくく、手軽にコンテンツを用意できるのが特徴です。
マンガ型
講義内容をストーリー性のあるマンガ形式で展開していくタイプです。
講義の導入部分や重要な部分のチェック(確認)テストなどにマンガを組み込んだり、講義に選択できる項目を設けたりして、ただマンガを読んで終わりとならないような工夫をされているケースが多く見られます。
6. 学習内容とeラーニングの内製/外部委託

eラーニングは学習内容によって、自社で独自に実施(内製)したり、外部サービス(外部委託)を利用したりと、内製と外部委託をうまく使い分けることが大切です。
内製と外部委託の分類
| 内製/外部委託 | 例 | |
|---|---|---|
| ①汎用的な教育研修 | 外部委託向き | ビジネスマナー、階層別研修、一般知識や手法 |
| ②専門性の高い教育研修 | 外部委託向き | コンプライアンスや会社法・契約書関連など法務知識 |
| ③自社独自の知識や ノウハウに関する教育研修 | 内製向き | 自社サービスや製品に関する技術情報や知識、 自社サービスや製品に関する販売知識や営業ノウハウなど |
| ④自社の業務に関する教育研修 | 内製向き | 業務システムの使用手順、経費精算の手順など |
外部から調達することで効率的に実施できるもの
「①汎用的な教育研修」「②専門性の高い教育研修」は外部から調達することで効率的に実施ができるでしょう。
汎用的な教育研修とは、どの企業でも共通して必要な会社ごとの独自性が必要ない教育研修です。外部委託先も多数ありますので、内容や価格などを比較し自社に合ったものを上手く利用しましょう。
専門性の高い教育研修も外部委託向きです。そもそも講師に適した専門知識を持った人材が社内にいない場合もありますし、人材がいたとしても教育研修実施に時間を割けないことが多いためです。
自社で独自に実施(内製)すべきもの
「③自社独自の知識やノウハウに関する教育研修」「④自社の業務に関する教育研修」は自社で内製すべきです。自社独自の知識やノウハウは、現場で日々携わっている社員に最も蓄積しており、外部委託することは難しい部分です。
内製する場合、eラーニングを実施するための仕組みや環境を一から十まで自社で用意する必要はありません。eラーニングに求める機能を明確にして、その要件を満たすASPサービスを利用したり、開発を外部委託したりして環境を整えます。
比較的安価に短期間で導入できるのが、すでにパッケージ化されているeラーニングサービス/eラーニング配信プラットフォームサービスの利用です。
次章では、eラーニングサービス/eラーニング配信プラットフォームサービスを利用して、内製でeラーニングを実施する場合について解説していきます。
7. 内製でのeラーニング実施に必要なもの
外部委託できない教育研修をeラーニング化する場合「Webサイト」と「学習コンテンツ」の準備が必要です。Webサイトはeラーニングサービス/eラーニング配信プラットフォームサービスを使い準備します。

Webサイトに必要な機能
《主な機能》
| ユーザー管理機能 | 受講者や管理者の登録や削除をする機能。 |
| 受講コースの作成機能 | 複数のコンテンツを学ばせる場合、学習順などを設定する機能。 |
| 受講期限設定機能 | 学習の期限の設定ができる機能。 |
| テスト機能 | 学習の理解度を確認するための機能。 受講時にリアルタイムに採点したり、合格の点数を設定できたりすると便利。 |
| 学習状況の把握機能 | 受講者の所属組織マネージャーなどに、受講者の学習状況が把握できる機能。 |
| アンケート機能 | 受講者に対して意見や感想をアンケート調査するための機能。 |
| お知らせ機能 | 受講者に対してお知らせ事項を表示する機能。 |
| 動画配信機能 | マルチデバイスに対応した動画配信。オンデマンド配信自体はもちろんのこと、 動画視聴(プレイヤー)に関する細かいコントロールもできると便利。 |
| 資料配布機能 | 学習資料や関連資料などの配布機能。 |
《場合によっては必要な機能》
| 修了証発行機能 | 受講内容によっては受講完了者に修了証が発行できると便利。 |
| 多言語対応 | 運用者/受講者によっては日本語以外の言語対応が必要な場合も。 |
| シングルサインオン | 自社用の既存システムとログイン認証を連携させることで、eラーニングサイトにログインする煩雑さを解消。 |
| Q&A機能 | 受講者と講師の質疑応答のための機能。 |
| SNS機能 | 受講者コミュニティ内のディスカッションや知識共有などコミュニケーションのための機能。 |
学習コンテンツの準備
教育研修は大別すると
- 知識やスキルを習得する
- 考え方(マインド)や行動を変える
の2種類に分かれます。
オンデマンド配信型のeラーニングは「知識やスキルの習得」に適しています。学習コンテンツのスタイルとしては、スライド資料や実演映像などを講師の説明と共に展開していくのが主流です。
研修の長さは様々ですが、1つの研修が短い方が学ぶ方にとっては受講しやすいといえます。日時が決まっている集合研修と異なり、eラーニングでは自ら学習のための時間を作り受講する必要があるためです。
1つの研修にかける最適な時間の正解は一律には決められませんので、受講者の環境やモチベーションなども視野に入れて検討していくのが望ましいといえるでしょう。
最近ではマイクロラーニング(Microlearning)とも呼ばれる、おおよそ10分以内の動画で1つのテーマを扱い、それをシリーズ化し、視聴を積み重ねていくことで知識やスキルの向上を図る教育手法にも注目が集まっています。
「考え方(マインド)や行動を変える」ための研修には、知識の習得だけではなくディスカッションやワークショップなどグループワークも有効です。グループワークには集合研修や、Web会議ツールを用いた双方向コミュニケーションでのオンライン研修が適しています。
オンデマンド配信型のeラーニングで実施する場合は「伝えたい内容がより受講者に響くよう訴求する」「優秀者や実体験者のインタビューを活用する」など工夫をすることで効果的に伝えることができるでしょう。
8. eラーニングでの動画活用
eラーニングを実施する際「学習資料を配布したので各自で読んで理解しなさい」というのは不親切です。

動画の効果
- テキストに比べてたくさんの情報が素早く伝わる
- 直接動画を見ることができるので又聞きより正確に伝わる
- テキストに比べてより記憶に残りやすい
動画の効果としては上記のような項目が挙げられます。さらに、若者を中心にテキストを読むことよりも動画視聴を好む傾向もあります。集合研修と同レベルの成果が得られるように動画活用を検討しましょう。
動画を準備するためには「プロフェッショナルに依頼して制作する」「自社スタッフで作る」といった方法があります。動画を自社スタッフで作る(内製する)ことで「費用が抑えられる」「好きなタイミングでいつでも作れる」「制作のための外部とのコミュニケーション時間が不要」などのメリットが得られます。一方、プロフェッショナルへ動画制作を依頼することで、社内の稼働を抑えつつ用途に適した質の高い動画を制作することができます。
動画内製の関連記事・お役立ち資料
9. eラーニングの実施に必要な費用

最後に、実際にeラーニングを導入する場合、どのくらいの費用が必要なのかを見ていきましょう。
eラーニングで必要になる費用は、次の2つです。
- 学習進捗を管理するための費用(例:初期費用やサービス利用料など)
- eラーニングコンテンツにかかる費用(例:制作費やライセンス料など)
これらの費用は、イントラネット型とクラウド型のいずれを採用するかでも異なるため、ここではコンテンツの提供形態における費用相場について解説します。
イントラネット型eラーニングシステムの費用相場
イントラネット型は、初期費用が必要なところが多く、毎月の運用コストも必要になるため、100万円以上の費用がかかるケースが多く見られます。
導入にともない、社内のインフラ整備のためにエンジニアを採用するなど、人件費もかかりやすい傾向です。そのため、ゼロから構築する場合には、開発費・人件費などを含めると数百万円程度の費用がかかることを見込んでおく必要があるかもしれません。
クラウド型eラーニングシステムの費用相場
クラウド側eラーニングシステムは、初期費用を含めた初月費用は10万円~40万円が相場です。ただし、サービス提供会社によっては初期費用が無料というケースがあり、相場よりも安く済む可能性があります。
料金形態は、1人あたりの従量課金制のほか、利用人数に応じて価格帯を設定している月額固定制があります。費用を抑えたい場合は、初期費用がかからないところや1人あたりの費用が安いeラーニングシステムを採用しましょう。
eラーニングシステムによっては、基本プランに動画配信機能が付いていない場合もあります。動画活用を前提とした場合は、動画配信機能の有無やその費用も確認しておきましょう。
10. まとめ
これからeラーニングに取り組みたい企業のご担当者様向けに、eラーニング導入前に知っておきたいことを解説しました。
社員教育・人材育成は会社のパフォーマンス向上にとって重要です。リモートワークや時差出勤など、働き方の変化により集合研修は開催・参加しにくい状況となりました。eラーニングは受講者にとって非常に利便性の高い学習手段といえます。「eラーニング導入は大変そう」「費用がかなり掛かるのでは?」と躊躇されていたご担当者様は、ぜひこの機会に前向きにご検討ください。
当社では、1000 IDが月額5万円で始められる動画eラーニングシステム「J-Stream ミテシル」を提供しています。J-Stream ミテシルは、教育・研修・情報共有など視聴者を限定した動画配信を、誰でも簡単に始めていただける動画eラーニングASPサービスです。クラウドサービスのためアプリのインストール不要で利用開始できます。30日間無料でお試しいただけますのでご興味のある方はお問い合せください。
「でもeラーニング用の動画がない」「動画を作る費用がない」といった企業様向けに、eラーニング用動画の内製に役立つ実践ガイドを配布中です。
動画作成未経験者でも、身近なツールを使って簡単にできるプレゼン動画作成方法を3つ紹介しています。ぜひダウンロードしてご活用ください。
動画eラーニング ソリューション
Jストリームは動画を活用した教育・研修を行うための動画eラーニングASPや動画配信プラットフォームを提供します。
関連記事
Jストリームの
ソリューションに
興味をお持ちの方は
お気軽に
お問い合わせください。