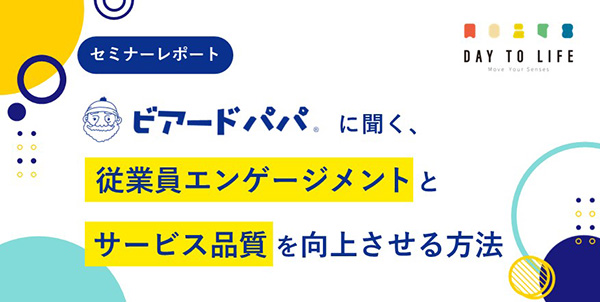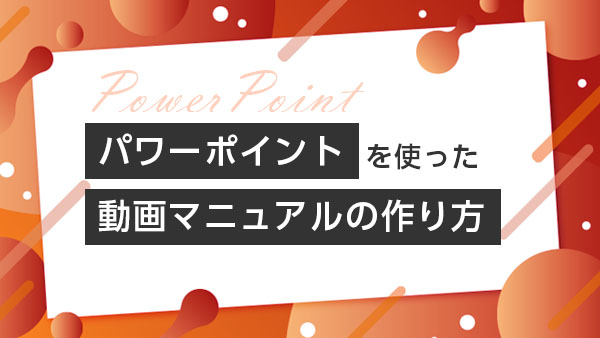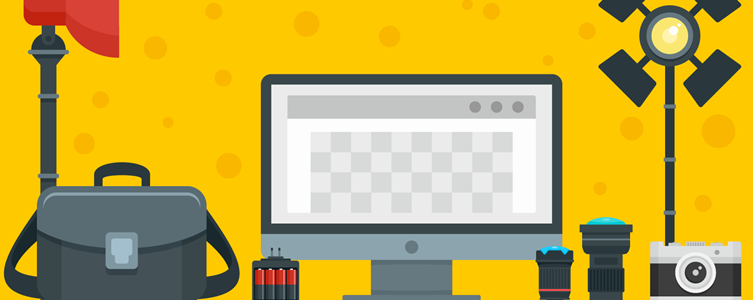「ビアードパパ」に聞く、従業員エンゲージメントとサービス品質を向上させる方法
2025.03.24
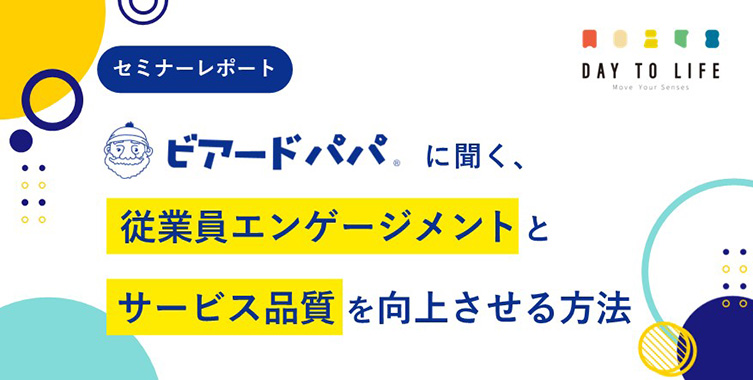
全国の店舗スタッフに向けたレシピ動画など多用途な動画配信を行っている、シュークリーム専門店「ビアードパパ」を運営するDAY TO LIFEの板垣氏をお招きし、従業員への情報発信で動画を活用することで、従業員エンゲージメントやサービス品質の向上に繋げた背景や、実際に発信している動画の内容、運用体制など、社内全体の働き方に変革をもたらした取り組みについて解説していただきました。
※本記事はJストリーム主催のオンラインセミナーを記事化したものです。
《 目次 》

1. 登壇者紹介


株式会社DAY TO LIFE
情報システム部 部長 板垣 智哉 氏
2001年に麦の穂(現DAY TO LIFE)に入社、直営店での勤務を経て、フランチャイズ担当SVとして東日本を担当。その後、営業推進部に異動し『POSシステムやお客様アンケートシステムなど、店舗営業支援システムの導入』『各種データの集計・分析業務』に従事。
現在は情報システム部で『店舗支援システム(ポイントアプリ、シフト申請、自動発注など)の導入』『「全社最適」を目指し、基幹システムのリプレースや新規システムの導入の推進』などに従事。


株式会社Jストリーム
マーケティング部 部長 小室 賢一
2004年、Jストリームに入社し、長期にわたり放送局、ポータルサイト、コンテンツプロバイダーの営業を担当。 新規顧客開拓部門のマネジメントを経て、現在はマーケティング部門のマネジメントを担当。
2. DAY TO LIFE紹介
板垣: 株式会社DAY TO LIFEは、シュークリーム専門店のビアードパパを中心に、さまざまなブランドでテイクアウトのスイーツショップを手がける企業です。「スイーツから、『よりよく生きる』を世界へ」というビジョンを掲げ、世界各国で店舗を展開しています。
![[セミナースライド]DAY TO LIFE様 事業概要](https://www.stream.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/blog_daytolife_20250319_002.jpg)
3. 外食産業が抱える課題感
小室: 最初にTechMagic株式会社が、外食産業が抱える課題をアンケート調査した「飲食産業の課題およびDX推進に向けた現状と展望レポート」をご紹介します。
![[セミナースライド]DAY TO LIFE様 外食産業が抱える課題感](https://www.stream.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/blog_daytolife_20250319_003.jpg)
小室: 最も多くの回答が集まったのは原価高騰で、次いで従業員の採用が進まない、人件費が高い、従業員の長時間労働と続きます。アンケートからは、特に人材不足を課題と感じる企業が多いことが見て取れます。
板垣: 弊社も同様で、原価高騰や人件費の影響は大きいですが、それ以上に深刻なのが人材不足です。必要な人員を確保できず新規出店に踏み切れないケースや、既存店でもシフトを埋められず、営業時間の短縮や休業を余儀なくされるケースも発生しています。これを解消すべく、新卒採用やインターンシップに力を入れると同時に、店舗オペレーションの省力化も図り、そういった場面で動画を活用しています。
外国人スタッフの採用について
小室: 人材不足を解消するため、外国人スタッフを採用する企業もありますが、御社はいかがですか。
板垣: ビアードパパは、お客さまからの注文を受けて製造する販売スタイルです。生地とクリームを組み合わせ可能なメニューもあり、お客さまとのコミュニケーションが欠かせません。言語の問題から、外国人スタッフの採用は極めて少ない状況です。
小室: オペレーションをできる人がいればよい、というわけではないのですね。課題とされている人材不足の解消には、新卒採用のほか、今在籍している従業員の方のエンゲージメント向上も必要なのだと感じますね。
4. サービス品質の均一化で、なぜ動画?
小室: 御社のように多店舗展開している場合、全店舗で均一のサービスを提供する必要があり、そのサービス品質の均一化のためにも動画を活用されているそうですね。
板垣: ビアードパパでは、店舗でシューを焼き、クリームも手作りしています。レシピはグループウエアで公開し、それを店舗で印刷して見ながら製造してきました。しかし、紙のレシピでは、クリームの混ざり具合や固さの伝達に限界があり、そういった点まで確認できる動画を活用することになったのです。
![[セミナースライド]DAY TO LIFE様 サービス品質の均一化で、なぜ動画?](https://www.stream.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/blog_daytolife_20250319_004.jpg)
小室: 確かに、言葉では表現しきれないことも、動画であれば正確に伝えられますね。
調査:コロナ禍以降に企画・運用した動画活用施策の内容
小室: もう一つ、動画活用の用途について調査したアンケート結果をご紹介します。
![[セミナースライド]DAY TO LIFE様 コロナ禍以降に企画・運用した動画活用施策の内容](https://www.stream.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/blog_daytolife_20250319_005.jpg)
小室: こちらの調査結果からは、コロナ禍以降、企業で動画による情報伝達が一般化し、幅広い用途で活用されていることがわかります。御社では、どういった種類、用途で動画を使っていますか。
動画コンテンツ例
板垣: レシピ動画や接客サービスの均一化を目指したマニュアル動画が多いです。そのほか、年頭のあいさつや期初の方針発表などのトップメッセージ、フランチャイズ加盟店のオーナーさま向けの総会動画もあります。オーナー総会は、以前は年1回集合で行っていましたが、コロナ禍以降配信に切り替えました。
![[セミナースライド]DAY TO LIFE様 動画コンテンツ例](https://www.stream.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/blog_daytolife_20250319_006.jpg)
小室: トップメッセージはエンゲージメントの向上、マニュアル動画はサービス品質の均一化が目的ですね。では、オーナー向けのオンライン総会の狙いは何でしょうか。
板垣: 総会は、本部の方針をオーナーさまにお伝えする重要な機会です。本部が伝えたいメッセージを繰り返し見ていただける点が、動画の一番のメリットだと感じています。
小室: 重要なメッセージだからこそ、確実に届ける方法として現在もオンラインを選択されているのですね。
5. 動画を配信している店舗数と対象人数
小室: これらの動画は、どれくらいの数の店舗や従業員の方に発信されているのでしょうか。
板垣: 現在、直営店と加盟店を合わせて全国に約280店舗あります。そこで働く約4,000名が配信の対象です。そのうち、実際に動画を視聴しているのは2,000名程度です。
![[セミナースライド]DAY TO LIFE様 動画を配信している店舗数と対象人数](https://www.stream.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/blog_daytolife_20250319_007.jpg)
小室: 店舗数や従業員数など、情報を届ける先が多い場合、先ほどのアンケートにもあるように、動画が効率的な情報伝達手段となりますね。
6. 人事部で実施している動画施策
小室: そして、採用のシーンでも動画を使われているそうですが、どのように活用されていますか。
板垣: 採用促進や、内定者・新入社員のエンゲージメント向上のために活用しています。弊社の新入社員研修は1年間にわたります。その様子を映像に残し、親御さんからのサプライズメッセージとともに編集し、研修最終日に上映しています。
動画を見ながら「いい会社だな」と会社への愛着が高まり、エンゲージメント向上につながると考えています。また、インターンシップでは、社内の部門紹介動画を流し、会社理解を促進しています。
![[セミナースライド]DAY TO LIFE様 人事部で実施している動画施策](https://www.stream.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/blog_daytolife_20250319_008.jpg)
小室: 感動的な動画で新入社員研修を締めくくり会社への愛着醸成につなげるのは、興味深い取り組みですね。
7. 動画配信の方法
小室: 次に、従業員の方に動画を届ける方法について教えてください。
板垣: Jストリームの法人向け動画共有・配信プラットフォーム「J-Stream Equipmedia」(EQ)で生成した動画プレーヤーを、グループウエア内に埋め込む形で掲載しています。レシピのような社外秘の動画はパスワードを設定し、グループウエア内でのみ閲覧可能にしています。
一方、内定者向けなど外部向け動画は、URLをお知らせし自由に視聴できるようにしています。
![[セミナースライド]DAY TO LIFE様 動画配信の方法](https://www.stream.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/blog_daytolife_20250319_009.jpg)
小室: 社内向けの動画が、従業員がよく利用するグループウエア内にあるというのはいいですね。また、セキュリティー設定が可能なプラットフォームを選び、コンテンツに応じて適切にセキュリティーコントロールされている点も効果的だと感じました。
8. 手探りの中で磨き上げた動画制作のスキル
小室: 動画制作や運用フローについても教えてください。
板垣: 動画は、人事部やマニュアル作成部門など複数の部門で制作しています。そして、情報システム部が申請書を受け付けて、公開や配信期間終了後の削除の運用をしています。
小室: 動画の活用には、動画を作り続ける運用体制もハードルの一つですが、御社にはもともと動画制作のノウハウはあったのでしょうか。
板垣: いえ、当初は動画制作が得意な社員に作ってもらっていました。現在は動画が重要なツールとして位置づけられており、それぞれの部門で業務として制作されています。
小室: これまでなかった動画制作業務が新たに加わったことで、最初は大変だったのではないかと想像しますが、いかがでしたか。
板垣: 本当に手探りだったと思います。ここに至るまで時間もかかりましたが、少しでも多くの人に必要な情報を届けるため、個々でブラッシュアップを重ねてきました。
![[セミナースライド]DAY TO LIFE様 手探りの中で磨き上げた動画制作のスキル](https://www.stream.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/blog_daytolife_20250319_010.jpg)
小室: 品質担保のためには動画が必要不可欠という使命感から、各部門でも動画制作が自分たちの業務として受け入れられていったのですね。
動画がエンゲージメント向上につながった実感は?
小室: エンゲージメント向上の面での成果があれば共有ください。
板垣: 動画の利点は、好きなタイミングで、繰り返し視聴できることです。会社のビジョンや業務マニュアルを動画で配信することで、より正確に伝わるようになったと思います。そのことが視聴する従業員のモチベーションやエンゲージメント向上につながっていると感じます。
小室: エンゲージメントはKPIで測りにくいものですが、情報を正確に届け続けることがエンゲージメント向上に重要で、その役割の一部を動画が担っているということですね。
板垣: はい、その通りです。
9. 各店舗における動画の視聴環境
小室: 次に、店舗スタッフ向けのマニュアル動画は、どういった環境で視聴されているのでしょうか。
板垣: 業務時間内に、各店舗に設置しているノートPCで見るのがルールです。レシピは社外秘ですので、セキュリティーの観点から、自宅など店舗外での視聴はNGとしています。
![[セミナースライド]DAY TO LIFE様 各店舗における動画の視聴環境](https://www.stream.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/blog_daytolife_20250319_011.jpg)
小室: これまでのお話の通り動画は非常に有用なものですが、デメリットを挙げるとすれば、視聴に時間がかかる点ですが、この点についてはどうお考えですか。
実際のレシピ動画
板垣: 視聴に時間がかかる点も意識しておりまして、特にレシピ動画は1分以内の尺に収まるようにしています。営業中に動画をゆっくり見ることはできませんから、いかに短時間で必要な情報を伝えるかが重要だと考えています。
![[セミナースライド]DAY TO LIFE様 実際のレシピ動画01](https://www.stream.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/blog_daytolife_20250319_012.jpg)
小室: そうですね。マニュアルは、わからない時にさっと確認し、すぐに作業に戻れるものであるべきですね。動画の尺は多くの企業の関心事ですが、視聴環境に応じて調整するのは重要なポイントだと思いました。ほかにも動画を見てもらうための工夫はしていますか。
板垣: 必要に応じてテロップを入れ、文字と映像で情報を伝えるようにしています。
![[セミナースライド]DAY TO LIFE様 実際のレシピ動画02](https://www.stream.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/blog_daytolife_20250319_013.jpg)
視聴状況の把握は実施している?
小室: 視聴状況の把握については、どういった運用をされていますか。
板垣: 導入当初は視聴状況を確認し、未視聴の場合は視聴を促していました。しかし現在は、業務をする上で動画の視聴が必要不可欠となっているため、視聴状況を確認することはなくなりました。
小室: そこまで動画が定着するには、時間がかかり苦労もあったと思います。定着した理由はどうお考えですか。
板垣: 時間はかかりましたね。レシピは紙と動画を併用していますが、繊細な作業工程では動画が欠かせません。新商品の発売前には必ず動画をアップしますが、そのタイミングが遅れると店舗から「動画はまだですか」と催促が来るほどに、今では動画が定着しました。
小室: 動画が、確実に必要な要素の一つに加わったのですね。
動画を活用する前の店舗スタッフ
小室: マニュアルの動画化にあたり、社内でネガティブな反応はなかったですか。
板垣: 導入当初、私は直接の担当ではありませんでしたが、記憶している限り反発はなかったと思います。
小室: マニュアルの動画化以前は、どのような形で情報伝達されていたのですか。
板垣: 新商品販売時には、事前にパティシエが講習会を開き、参加者が集まる仕組みでした。中にはパティシエの説明を動画で撮る人もおり、「動画を配信すればより多くの従業員に伝えられる」という発想から動画を導入しました。
小室: 動画の導入により、講習会に割かれていたパティシエのリソースが解放されたこともメリットと言えそうですね。
10. 「紙」と「動画」の使い分け
小室: 先ほど、レシピは紙と動画を併用されているとのことでしたが、それぞれどのように使い分けをしていますか。
板垣: 材料の分量などは、やはり紙で確認する方が早いです。一方、クリームの固さなどは動画でなければ伝わりにくく、それぞれのメリットを活かして使い分けています。
![[セミナースライド]DAY TO LIFE様 「紙」と「動画」の使い分け](https://www.stream.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/blog_daytolife_20250319_014.jpg)
小室: 雰囲気や固さ、動かすスピードといった情報を正しく伝えられる点は動画の強みです。動画の特性をしっかり把握し、効果的に活用されていることが、今のお話からも伺えました。
FC加盟店・直営店の教育方法の違い
小室: 御社には、直営店とフランチャイズ加盟店の2種類の店舗運営手法がありますが、教育方法に違いはありますか。
板垣: 直営店では、各店舗の店長や社員がOJTでアルバイトの教育をしています。加盟店でも基本的には同様の対応をしており、本部サポートとして本部スタッフがアルバイト向けの研修を実施することもあります。直営店と加盟店で教育方法に若干の違いはありますが、どちらもサービスの均一化を目指して取り組んでいます。
小室: ではここで改めて、動画を運用する中で感じる動画のメリットを教えてください。
板垣: 動画は一度作れば、何度でも活用できる点がメリット。多くの方に、それぞれのタイミングで見てもらうことができます。結果として、本部にとっても時間と費用の削減につながると感じます。
小室: 回り回って人材不足解消につながる重要な取り組みになっているということですね。ありがとうございます。
11. 今抱えている課題、動画に関わる今後の展望
小室: 最後に、今抱えている課題や今後の展望をお教えください。
板垣: 以前から、EQを利用してきましたが、実はこれまで、動画ポータルサイトを作成する機能をまったく使ってきませんでした。しかし、この機能を活用することで、動画の利用範囲が広がり、教育や情報発信の最適化を目指せるのではないかと考えています。
動画のさらなる有効活用が、エンゲージメントやサービス品質の向上につながり、それが人材不足の解消にもつながると期待しており、今後も動画の取り組みを強化していきたい考えです。
![[セミナースライド]DAY TO LIFE様 今抱えている課題、動画に関わる今後の展望](https://www.stream.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/blog_daytolife_20250319_015.jpg)
小室: ありがとうございます。今回はDAY TO LIFEさまから、体制やノウハウなど具体的で、かつ貴重なお話をお伺いできました。Jストリームとしても引き続き動画の活用支援を通じて、御社の業績や課題解決に貢献させていただければと思います。
関連サービス
法人向け動画共有・配信プラットフォーム「J-Stream Equipmedia」(EQ)
関連記事
Jストリームの
ソリューションに
興味をお持ちの方は
お気軽に
お問い合わせください。