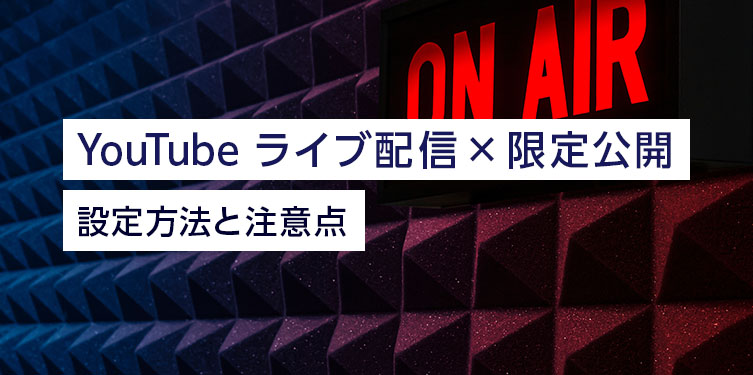
YouTubeのライブ配信を行う際、公開範囲を「限定公開」に設定することで視聴者を特定の方に限定できます。限定公開機能は便利ですが、利用する際には注意すべき点もあります。この記事では、YouTubeの限定公開機能の概要や具体的な設定手順、利用にあたっての注意点についてご紹介します。
なおライブ配信ではなく、オンデマンド配信の動画をYouTubeで限定公開に設定する方法については、こちらの記事「YouTube「限定公開」で動画を共有する方法と注意点」で詳しく解説しています。
1. YouTubeライブ配信 限定公開とは?

YouTubeでライブ配信を行う際に限定公開機能を利用すると、YouTube上の検索結果やおすすめなどに表示されなくなります。つまり、その配信URLを知っている方のみがアクセスできます。
ただし、URLを知っている人が第三者に教えたりSNSで拡散したりすれば、誰でも配信を視聴できてしまうので注意が必要です。
YouTube 限定公開にパスワードをかけることはできるか?
YouTubeの限定公開で配信するライブ配信に視聴パスワードをかけることはできません。
非公開であれば、アカウント管理者が指定したユーザーだけが視聴できますが、視聴させたい相手がGoogleアカウントを持っている必要があります。そのため、企業用途では適さない場合もあるでしょう。
そういった場合は、Jストリームの「J-Stream Equipmedia」(EQ)など、企業用途に適した動画配信プラットフォームの使用がおすすめです。ビジネス用途など、視聴者をしっかりコントロールしたライブ配信を行いたい場合は利用を検討してみてください。
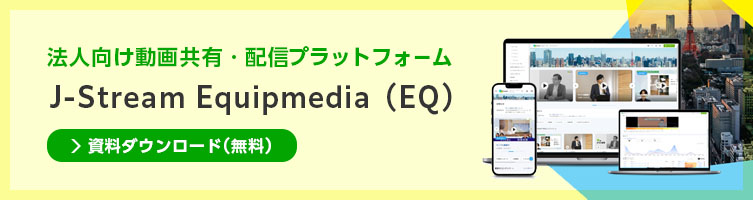
公開・限定公開・非公開の違い
YouTubeでライブ配信を行う際には「非公開」「限定公開」「公開」の3段階でプライバシー設定が行えます。それぞれの違いは以下のとおりです。
非公開
非公開に設定すると、配信者と許可されたユーザーしか視聴できません。非公開の動画を視聴するためには、視聴者がGoogleアカウントを登録した上で、配信者が視聴者のメールアドレスを指定する必要があります。
限定公開
限定公開に設定すると、そのライブ配信のURLを知っている方だけが配信を視聴できます。検索結果や関連動画、おすすめとして配信が表示されることはありません。
公開
ライブ配信を公開に設定すると、誰でも配信の視聴が可能です。また、検索結果やおすすめなど、YouTube上のあらゆる場所に配信が表示されます。
こちらは、それぞれの設定による違いをまとめた表です。
| 機能 | 非公開 | 限定公開 | 公開 |
| ライブ配信のURLを共有できるか | × | ○ | ○ |
| 配信者のチャンネルのセクションに配信を追加可能か | × | ○ | ○ |
| 検索結果、関連動画、おすすめに表示される可能性があるか | × | × | ○ |
| 配信者のチャンネルにライブ配信が投稿されるか | × | × | ○ |
| 視聴者の登録チャンネルのフィードに表示されるか | × | × | ○ |
| コメントを投稿可能か | × | ○ | ○ |
| 公開再生リストに表示可能か | × | ○ | ○ |
2. YouTubeライブ配信 限定公開の設定方法
YouTubeのライブ配信で限定公開設定を行うためにはどうすればよいのでしょうか。以下では、設定の流れを具体的にご紹介します。
事前準備
まずは、YouTube上でライブ配信を行うための準備を行います。
ライブ配信を行うためには、YouTubeアカウントが必要です。アカウントの作成直後は、ライブ配信をはじめとする一部機能が利用できないことに注意してください。制限を解除するためには、YouTube Studioから電話による利用資格の認証確認が必要です。
その後YouTubeアカウント上でライブ配信を有効化することで、ライブ配信を開始できるようになります。
あわせて、カメラやマイクなどの機材を準備します。なおYouTubeでは、ウェブカメラやスマートフォンなどに加えて、ソフトウェアやハードウェアのエンコーダーを利用した配信も可能です。
ライブ配信の開始と公開範囲の設定
ライブ配信を開始するためには、YouTubeホーム画面の右上にあるビデオのアイコンをクリックし、「ライブ配信を開始」を選択します。タイトルやサムネイル、配信内容の説明、チャットの有効化などを設定しつつ、最後に公開範囲を指定します。
公開範囲は、上述の「非公開」「限定公開」「公開」の3つから選択可能です。ここで「限定公開」を選択することで、限定公開としてライブ配信が開始されます。
ライブ配信の開始とURLの共有
設定が完了すると、ライブ配信の開始画面が表示されます。ここで「共有」ボタンを押すとライブ配信を視聴するためのリンクが表示され、このリンクを共有された方が配信を視聴できるようになります。
最後に「ライブ配信を開始」ボタンを押し、ライブ配信を開始します。なお、ライブ配信を開始した後に公開範囲を変更することも可能です。
3. YouTube ライブ配信実施時の注意点

YouTubeは無料で使える魅力的な動画配信プラットフォームです。しかし、利用時には注意すべき点があります。
利用規約・コミュニティガイドラインを守る
YouTubeでライブ配信を始める前には、利用規約やコミュニティガイドラインの理解が重要です。無料で使えるサービスでも、ルールを守らなければ配信停止やアカウントの制限・削除などのペナルティを受ける可能性があります。
著作権への配慮が必要
音楽や映像など配信内容に関する著作権へは配慮が必要です。音楽を使用する場合は著作権フリーのものや、YouTubeが許可している音楽などを使用しましょう。ライブ中に流す映像についても自社が著作権を保有している、または使用する権利を有しているものを用います。無断で使用するとペナルティを受ける可能性があります。
ライブ配信にスライド資料を用いる場合は、資料の中身も確認する必要があります。
チャットコメントの管理が必要
ライブ配信のチャットを加えて「質問を受け付けやコミュニケーションを取りたい」「コメントで参加者の体験を高めたい」「配信を盛り上げたい」と考える場合もあるでしょう。チャットでは配信内容にふさわしくない投稿がされる可能性もあります。不適切な投稿を防ぐためには、事前にコメントフィルターを設定しましょう。また、管理者を配置しライブ配信中もコメントの管理を行いましょう。
端末やネットワークによってはYouTubeを視聴できない場合もある
会社が貸与しているパソコンといった端末や企業のネットワークでは、YouTubeの視聴ができないように設定している企業もあります。企業向けの配信では、視聴対象者がYouTubeを視聴できるか事前に確認する必要があります。
公開範囲設定は適切におこなう
「範囲を限定して配信していたつもりが、想定しない人に視聴されてしまった」そんなことにならないために、公開、限定公開、非公開の特長をしっかり理解し、正しい設定でライブ配信を実施しましょう。
4. セキュアにライブ配信をする方法とは?
ここまで、YouTubeのライブ配信における限定公開設定について、その実施方法や注意点について解説しました。記事中でもご紹介したとおり、YouTubeのライブ配信における限定公開機能では、視聴対象者以外が動画を視聴するリスクを完全に排除することは難しいといえるでしょう。
リスクを避けるには、法人向け動画配信プラットフォームを活用して、セキュリティが確保されたライブ配信の実施をおすすめします。
当社は、企業における使いやすさと充実した機能を備えた動画共有・配信プラットフォーム「J-Stream Equipmedia(EQ)」を提供しています。
EQ事例:Sky株式会社 様
様々なオンラインイベントの動画配信にJ-Stream Equipmediaを利用、“より多くの方に視聴いただきやすく”かつ“イベント運営負荷や配信トラブルリスクも軽減”
「企業によっては利用/視聴が制限されている場合もあります。またセキュリティやコンテンツ保護の観点も大事です。加えて、当社ではイベント後にフォローをするために、どういった方が視聴してくださったかという情報も取得したいと考えていましたので、YouTubeは適していませんでした。」
EQは
- 特定の視聴者だけに制限して動画配信を行うために必要なセキュリティ設定機能
- ユーザー認証型ポータルサイトをすぐに公開できる機能「EQポータル」
- 情報漏洩対策やコンテンツ保護に対してより高いレベルで対応したい企業様向け「暗号化配信機能」
などを有しています。
オプションで、動画ファイルダウンロード用URLの時限付きトークンとの連携機能などが設定可能です。また、再生ドメイン制限については、プレイヤー単位ではなく動画単位で行うことができます。
30日間無料でお試しいただけます。ご興味のある方はお問い合わせください。
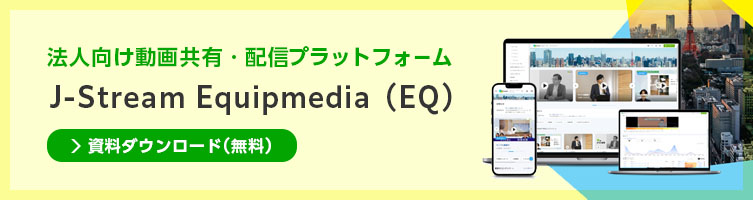
また、Jストリームは動画配信・ライブ配信の実績を有しています。ライブ配信自体もお任せしたいという場合は、ぜひご相談ください。
経験豊富なライブ配信スタッフがお客様毎に専任でサポートいたします。案件ごとにチームを組み、それぞれの役割を持ったスタッフが、常に情報を連携し、確実な配信の実現に向けて対応、企画・ライブ中継現場の対応から最新テクノロジーのご提案まで、トータルサポートいたします。
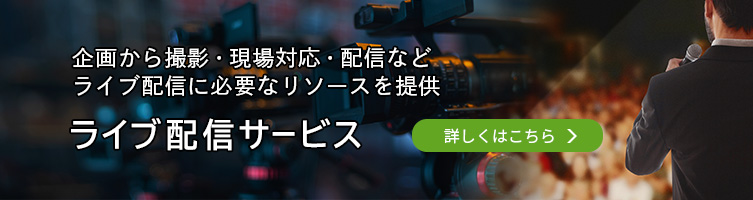
関連記事
Jストリームの
ソリューションに
興味をお持ちの方は
お気軽に
お問い合わせください。











